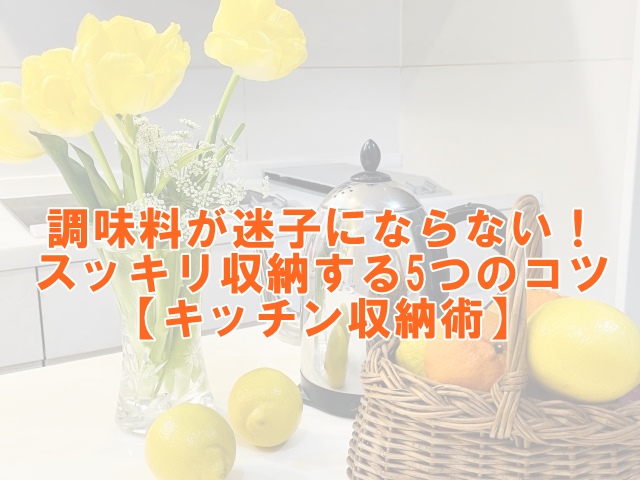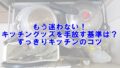料理中、「あれ、しょうゆどこ?」「みりんが見つからない…」と、調味料を探して立ち止まってしまうこと、ありませんか?
特に忙しい日や時間が限られているときには、この“ちょっとした探し物”が意外とストレスになりますよね。
そんなお悩みを解決してくれるのが、調味料の「立て収納」。
上から一目で見えるように並べることで、使いたい調味料がすぐに手に取りやすくなり、キッチン作業が驚くほどスムーズになります。
この記事では、誰でも簡単に取り入れられる立て収納のメリットや、実際に使ってみたビフォーアフター、続けやすくするための工夫まで、たっぷりご紹介します。
100均アイテムや身近なグッズで今日からできるアイデアが満載!ぜひご自宅のキッチンでも試してみてくださいね。
1. なぜ調味料は立てて収納したほうがいいの?

探す時間ゼロ!一目で見渡せる安心感
キッチンで料理中、「あれ?しょうゆどこ?」「塩が見当たらない…」と、調味料を探して手が止まったことはありませんか?そんなときに便利なのが“立て収納”。上から見渡せるように収納することで、使いたい調味料がパッと見つかり、探す手間がなくなります。
限られたスペースを効率的に使える
調味料を横に並べてしまうと、場所をとってしまううえに重なり合って見えにくくなることも。立てて収納すれば、引き出しや棚の中の高さを活かして、省スペースに整理できます。狭いキッチンでも使いやすく、無駄な空間がなくなります。
小瓶も安定!倒れない安心収納
スパイスボトルや小さめの調味料容器は、倒れやすくて扱いにくいもの。でも立てて収納することで、しっかり固定できて安定感がアップ。容器が転がる心配もなくなり、取り出しもスムーズになります。
2. 立て収納におすすめのアイテムは?

100均で揃う!コスパ最強アイテムたち
まず注目したいのは、手軽に揃えられる100均グッズ。ダイソーやセリア、キャンドゥなどでは、調味料の立て収納にぴったりな「ペン立て」や「仕切り付きトレー」「カトラリースタンド」などが充実しています。これらは調味料のサイズに合わせてカスタマイズしやすく、複数を並べてもスッキリまとまるのが魅力。仕切りがあることで、瓶同士が倒れたりぶつかったりするのを防げるのもポイントです。
無印良品のアクリルケースで“魅せる収納”
見た目もこだわりたい人には、無印良品のアクリルボックスや木製ボックスもおすすめ。透明で中身が見やすく、シンプルなデザインなのでどんなキッチンにもなじみます。高さや横幅もシリーズで統一されているため、スペースに合わせて自由に組み合わせられるのが便利です。上品な「見せる収納」としても優秀で、ラベルを貼ればさらに美しく整理できます。
調味料専用スタンドや回転式ラックも便利
最近は、調味料の立て収納専用に設計された「スパイスラック」「ボトルスタンド」なども多く販売されています。中でもおすすめなのが「回転式ターンテーブル」。棚や冷蔵庫内でもくるっと回すだけで奥の調味料に簡単にアクセスでき、立て収納の弱点だった「奥の取り出しにくさ」も解消してくれます。
手持ちの空き箱や収納グッズを活用してみよう
市販のアイテムだけでなく、お菓子の空き箱や靴用の収納ケースなどを再利用するのも立派な収納術。高さが合えば、小瓶を仕切って収納するのにちょうどいいサイズになることも。コストをかけずに工夫してみるのも、キッチン整理の楽しさのひとつです。
3. 実際に収納してみたビフォーアフター

ビフォー:調味料がごちゃついて使いづらい状態
収納前のキッチンは、引き出しの中に調味料がバラバラに置かれていて、必要なときに見つからないこともしばしば。瓶が横になっていたり、重なってしまってラベルが読めなかったり、使いかけの調味料がいくつも出てきて「同じものを二重に買ってしまった…」なんてことも。料理中に立ち止まる回数が多く、時短どころかストレスが溜まってしまう原因になっていました。
工夫したポイント:100均アイテムで仕切り+立て収納
そんな状態を改善すべく、まずは100均で購入した「仕切り付きケース」や「深めのペン立て」を使って立て収納に挑戦。調味料のボトルの高さに合わせて容器を選び、ラベルが見える向きに並べることで、視認性も抜群に。さらに使用頻度に応じて手前・奥の配置を調整し、取り出しやすさも意識しました。
アフター:スッキリ整って使いやすさ倍増!
収納後の引き出しは、まるでお店の陳列棚のように整然と並び、使いたい調味料がひと目で分かる状態に。どの容器も倒れることなく立っており、取り出しもスムーズ。調味料の量が減っても空間が乱れにくく、補充や買い足しのタイミングも一目瞭然に。毎日の料理が格段にスムーズになり、時間の節約だけでなく、キッチンに立つモチベーションもアップしました。
見た目のスッキリ感で気分も上がる
ビフォーの「雑然とした引き出し」から、アフターの「整った収納スペース」へ。たった数百円のアイテムとちょっとの工夫で、キッチンの印象がガラッと変わる体験はとても爽快です。「収納の力ってすごい!」と改めて実感できる結果となりました。
4. 立て収納をさらに便利にするコツ

コツ①:ラベルは「上向き」に貼って一目でわかる
調味料を立てて収納する際に意外と見落としがちなのが“ラベルの向き”。引き出しなどの上から見下ろす収納の場合、ボトルの正面ではなく「キャップの上部」や「フタの天面」にラベルを貼るのがポイントです。名前を見ただけで迷わず手に取ることができ、調理中でもスムーズな動線を確保できます。ラベルはテプラや100均のシールを活用すれば、おしゃれで実用的に仕上がります。
コツ②:色や用途で分類して整理しやすく
立て収納の中でも、さらに探しやすくするには「色分け」や「用途別分類」がおすすめです。例えば、白いキャップは甘味系、黒いキャップはスパイス系、というようにカラーでグルーピングしたり、「炒め物でよく使うセット」「お弁当用の味付けセット」など使用シーンで分けると、調理時の迷いも減ります。ボックスごとに分ければ、そのまま引き出して使えるので、時短にもつながります。
コツ③:よく使う調味料は“ゴールデンゾーン”に
使いやすさをさらにアップさせるには、使用頻度の高い調味料を「手前」や「目線の高さ」に配置するのが鉄則。人が自然に手を伸ばしやすい範囲“ゴールデンゾーン”に置くことで、取り出しの手間が格段に減ります。逆に、使用頻度が少ないものは奥や下段へ。日常の動きを観察して、自分にとってベストな配置を見つけてみましょう。
コツ④:回転トレー(ターンテーブル)で奥まで使いやすく
冷蔵庫や深めの棚に立て収納する場合、奥の調味料が取りづらくなるのが難点。そんなときに役立つのが「回転式ターンテーブル」です。台座ごとクルッと回せるので、奥の調味料にもラクに手が届きます。スパイス類やオイルボトルなど、形状がバラバラなものをまとめるのにもぴったり。収納効率と取り出しやすさの両方を叶えてくれる、便利グッズのひとつです。
コツ⑤:家族にもわかる収納ルールを
せっかく整えた収納も、自分しかルールを知らなければ維持が難しくなってしまいます。家族みんなが使うキッチンだからこそ、「このケースには◯◯系調味料を」「使い終わったら必ずここへ戻す」といった、簡単なルールを共有しておくと◎。とくに子どもやパートナーが料理をする機会があるご家庭では、誰でも迷わず使える状態がキープされやすくなります。
「私はこうしているよ」:家族にも分かりやすい工夫を
我が家では、調味料を用途ごとに分類してカラーラベルで分けています。たとえば「和食用」は赤、「中華用」は黄色、「洋食用」は緑といった具合。家族が調理を手伝うときも「赤いところにあるよ」と伝えるだけで目的の調味料がすぐ見つかるので、誰でも分かりやすい環境になりました。
さらに、調味料のキャップ部分にマスキングテープを貼り、油性ペンで「しょうゆ」「みりん」などと手書きでラベルしています。これなら特別な道具がなくてもすぐに取り入れられて、書き換えも簡単。見た目もやわらかく、手作り感があってキッチンに温かみが出るのもお気に入りポイントです。手軽にできる工夫が、家事ストレスの軽減につながっていますよ。
5. 続けやすい仕組みにするには?

“定位置”を決めるのが収納を長続きさせるカギ
どんなにキレイに整えた収納も、使ったあとに元に戻せなければ、あっという間に元の状態に逆戻りしてしまいます。続けやすい収納にするために最も大切なのは、「この調味料はここ」と場所を固定する“定位置ルール”をつくること。立て収納なら、調味料の形や高さに合わせてスペースを確保しやすいので、場所さえ決めておけば自然と整いやすくなります。
買い足した時もすぐしまえる仕組みづくり
調味料の買い足しや補充のたびに収納をやり直すのは、手間がかかって続かない原因に。そこでおすすめなのが、「空きスペース」をあらかじめ確保しておくこと。使用頻度が高く、回転の早い調味料の周辺に少し余裕を持たせることで、新しく買ったものも迷わず定位置に収まり、無理なく収納が維持できます。
“使う→戻す”が自然になる動線を考える
調味料を使って戻すときに、無理なく自然に手が伸びる配置にしておくと、片付けが面倒に感じにくくなります。たとえば、コンロ近くの引き出しには炒め物でよく使うオイル類やしょうゆを、レンジや調理台近くにはソースやケチャップを、というように「使う場所としまう場所」を近づけておくと、使い勝手がグッと良くなります。
家族にも伝わる“誰でも使える収納”へ
キッチン収納を自分だけのルールで作ってしまうと、他の家族には使いづらくなってしまいがちです。続けやすくするには、家族みんなが迷わず使えるよう、シンプルで明確なルールにすることが大切。ラベルや分類のルールを家族と共有しておけば、誰かが調理中でもサポートしやすくなり、家族みんなで“片付くキッチン”を維持できるようになります。
完璧を求めず「ゆる収納」でもOK
最初から完璧な収納を目指すと疲れてしまい、逆に長続きしないこともあります。大切なのは、自分や家族にとって使いやすい状態が保たれていればOK!という気持ち。日々の変化に合わせて少しずつ調整しながら、“なんとなくスッキリ”を目指すだけでも十分に効果があります。無理のない範囲で、気楽に楽しみながら続けていきましょう。
まとめ

調味料の収納に悩んでいた毎日も、立て収納を取り入れることで驚くほどスムーズに変わります。上から見渡せてすぐに取り出せる立て収納は、料理の時短につながるだけでなく、キッチンの見た目もスッキリと整えてくれます。
100均アイテムや家にあるグッズを使えば、コストをかけずに手軽に始められるのも魅力。ラベルや色分けなど、ちょっとした工夫で使い勝手はさらにアップします。
「定位置を決める」「使いやすい動線にする」「家族と共有する」といったポイントを押さえれば、長く続けられる仕組みづくりも可能に。
毎日立つキッチンだからこそ、小さなストレスを手放して、心地よい空間にしていきたいですね。まずはお気に入りの容器や収納ケースを手に取って、一歩目の立て収納、始めてみませんか?