毎日の料理でよく使う片手鍋。味噌汁やスープを作ったり、ちょっとした煮物をしたりと、キッチンに欠かせない存在ですよね。
でも実際に選ぼうとすると「16cmと18cm、どちらが良いのだろう?」と迷ってしまう方は多いのではないでしょうか。
数字で見るとたった2cmの違いですが、容量や調理シーン、収納のしやすさなどに大きな差が出るんです。
この記事では、片手鍋の基礎知識から、16cmと18cmの違い、料理別の使い分け方や人気ブランドまで、初心者の方にもわかりやすく丁寧に解説していきます。
あなたのライフスタイルにぴったりのサイズを選べるように、実用的なチェックリストや判断フローチャートもご用意しました。
片手鍋を正しく選べば、毎日の料理がぐっと楽になり、台所に立つ時間がもっと快適になります。
ぜひ最後まで読んで、あなたに合った一品を見つけてみてくださいね。
1. 片手鍋の基礎知識

1-1. 片手鍋とは?その魅力と特徴
片手鍋とは、その名のとおり片方に長いハンドルが付いた鍋のことを指します。
両手鍋に比べて軽量で持ちやすく、片手でさっと持ち運びやすいのが特徴です。
少量の煮物や汁物、また牛乳を温めたりソースを作ったりと、日常のちょっとした調理にとても便利に使えるアイテムです。
特に女性や一人暮らしの方にとっては「取り回しのしやすさ」が魅力で、コンロから食卓へそのまま持っていける手軽さや、洗い物の少なさなどもメリットのひとつです。
また、片手鍋はサイズ展開が豊富なので、ライフスタイルに合わせて選べる自由さも人気の理由です。
1-2. よく使われるサイズと一般的な用途
片手鍋にはさまざまなサイズがありますが、家庭でよく選ばれるのは14cm、16cm、18cm、20cmあたりのサイズです。
・14cmは少量のスープや離乳食、ソース作りにぴったり。お弁当のおかずを少しだけ煮たいときにも活躍します。
・16cmは一人暮らしや二人分の味噌汁に最適で、最も使い勝手の良いサイズとして人気です。
・18cmは二人暮らしから小さなお子さんがいる家庭におすすめで、煮物やカレーを少量作るのに向いています。
・20cmになると三〜四人分の料理に対応でき、家族向けとして本格的に活躍するサイズです。
このように片手鍋は、サイズによって「誰に向いているのか」「どんな料理に適しているのか」が変わります。
自分のライフスタイルを考えながら選ぶことで、毎日の料理がぐっと効率的になります。
1-3. 素材ごとの特徴(ステンレス・アルミ・ホーローなど)
片手鍋を選ぶときには、サイズだけでなく素材の違いも大切なポイントです。
素材によって熱の伝わり方や重さ、見た目のおしゃれさが変わり、使い心地にも大きな影響があります。
ステンレスは丈夫で長持ちし、酸や塩分に強いのが特徴です。
焦げ付きにくく保温性も高いため、味噌汁や煮物など幅広く使えます。
少し重さはありますが、お手入れのしやすさから人気があります。
アルミはとても軽く、熱伝導が良いので短時間で料理を仕上げたいときに便利です。
ただし長時間の煮込み料理にはあまり向きません。
価格が比較的手頃なのも嬉しい点です。
ホーローはガラス質でコーティングされているため、見た目がおしゃれで色合いも豊富です。
匂いや色移りがしにくく、煮込み料理に向いていますが、強い衝撃に弱く欠けやすいという注意点もあります。
このように素材ごとに特徴があるので、料理スタイルや好みに合わせて選ぶと、毎日のお料理がより快適で楽しくなります。
2. 16cmと18cmの違いを徹底解説
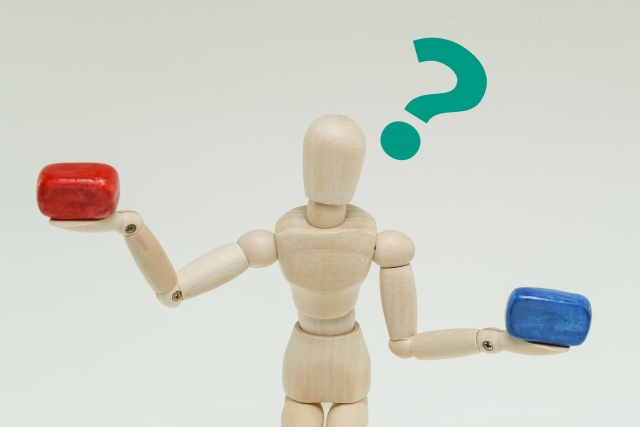
2-1. 容量の違い(具体的なml・人数目安)
片手鍋を選ぶ際にまず注目したいのが「容量」です。
16cmと18cmの違いは数字だけ見るとわずか2cmですが、実際の容量には意外と大きな差があります。
一般的に16cmの片手鍋は約1.5〜1.8リットルほどの容量があり、一人暮らしや二人分程度の汁物にちょうど良いサイズです。
たとえば、毎日のお味噌汁を二人分作る場合や、牛乳を温めたりインスタントスープを作るときに便利です。
一方で18cmの片手鍋は約2.0〜2.3リットルとやや大きめで、三人分以上の料理をカバーできます。
小さなお子さんがいる家庭や、食べ盛りの学生さんがいる家庭では18cmを選んだ方が安心です。
つまり、16cmは「少人数向けの省スペースサイズ」、18cmは「少し多めに作りたいときの頼れるサイズ」という位置づけになります。
2-2. 調理シーン別の使いやすさ比較
実際に料理をするとき、どのようなシーンで16cmと18cmの違いを感じるのでしょうか。
汁物の場合:味噌汁やスープを作るなら、16cmは二人暮らしにぴったり。
余分に残さず、ちょうど良い分量を作れます。
18cmは三人以上の家族向けで、おかわり分までしっかり作れる安心感があります。
煮物の場合:肉じゃがや筑前煮などを作る場合、16cmでは一度に作れる量がやや少なめで「二人でちょうどよく食べ切れる量」に向いています。
18cmなら翌日分まで保存できるくらいの量をまとめて調理でき、作り置きしたい方におすすめです。
インスタント麺の場合:一人分のカップラーメンや袋麺を茹でるなら16cmでも十分ですが、二人分を同時に作ろうとすると少し窮屈に感じます。
18cmなら二人分の麺を同時に茹でられるので、時短にもつながります。
このように、調理シーンによって「ちょうど良さ」が変わるので、自分の暮らし方に合ったサイズを選ぶのが大切です。
2-3. 収納・キッチンスペースの観点
キッチンがコンパクトなご家庭では、収納のしやすさも鍋選びの重要なポイントになります。
16cmの片手鍋は直径が小さい分、シンク下や食器棚にもすっきり収まり、重ねて収納しやすいのが特徴です。
一人暮らし用の小さなキッチンや、調理道具が限られているご家庭ではとても扱いやすいサイズです。
一方で18cmの片手鍋は、直径が大きくなることで「他の鍋と重ねづらい」「収納スペースを圧迫する」と感じる方もいます。
ただ、その分多用途に使えるため、「多少スペースを使っても便利さを優先したい」方には向いています。
収納スペースが限られている場合は、16cmを選んで「普段使い用」とし、必要に応じて大きな鍋を追加するスタイルもおすすめです。
2-4. 重さと扱いやすさの違い
同じ素材で作られた場合でも、サイズが大きくなると当然ながら重量も増します。
16cmの片手鍋は軽くて取り回しがしやすく、片手でさっと持ち上げて中身を器に移す動作も楽にできます。
特に女性や力に自信がない方にとっては、毎日使う道具は「軽さ」が大きな魅力になります。
18cmの片手鍋は、容量が大きい分だけ食材や水を入れると重量が増し、持ち上げるのに少し力が必要です。
中身が熱い状態で移動させるときには、安定感がある反面、重さで少し不便に感じる場合もあります。
軽さを優先するなら16cm、調理量の多さや作り置きの便利さを優先するなら18cmといったように、ライフスタイルに応じて選ぶことがポイントです。
3. 料理別おすすめ活用法

3-1. 味噌汁やスープはどちらが便利?
毎日の食卓に欠かせない味噌汁やスープは、鍋のサイズ選びがとても重要です。
16cmの片手鍋は、二人分くらいの味噌汁を作るのにぴったり。
余らせずに食べ切れる量を作れるので、いつでも新鮮で温かい味噌汁を楽しめます。
スープも同じで、コーンスープやコンソメスープなどをちょっと作りたいときに便利です。
一方で18cmの片手鍋なら、三人以上の家族や「おかわりを想定したい」場合に最適です。スープジャーに入れてお弁当に持っていく分まで作れるのも嬉しいポイント。
人数や作りたい量に応じて、16cmと18cmで大きく使い勝手が変わります。
3-2. カレー・シチュー・煮物に向くのは?
カレーやシチュー、肉じゃがなどの煮込み料理は、具材が多くなるため鍋のサイズ選びが結果に大きく影響します。
16cmの鍋では、二人分くらいのカレーを一度に作るのが限界で、具材もやや少なめに調整する必要があります。
小ぶりなお鍋で作るとすぐにいっぱいになってしまうため、量を抑えたい方や「食べ切りサイズで作りたい方」に向いています。
18cmの鍋は余裕を持って具材を入れられるので、煮崩れしにくく味も均一に染み込みやすいです。
翌日の分までまとめて作り置きしたい、少し多めに仕込んで冷凍保存したいといった方には18cmが安心です。
家族向けの「定番おかず」には18cmが頼れる存在になります。
3-3. ラーメン・パスタをゆでるなら?
インスタントラーメンやパスタをゆでるシーンでも、鍋のサイズ差がはっきり出ます。
16cmの片手鍋は、一人分のラーメンや少量のパスタをゆでるのにぴったり。
お湯の量も少なくて済むため、短時間で調理が完了し光熱費の節約にもつながります。
ただし二人分を同時に作ろうとすると、16cmでは窮屈になり、麺がくっつきやすくなることもあります。
18cmの鍋なら二人分を一度にゆでても余裕があり、湯切りもしやすいです。
「一人分をさっと作りたい」なら16cm、「複数人分を同時に仕上げたい」なら18cmと考えるとわかりやすいですね。
3-4. お弁当用・少量調理の便利さ
お弁当のおかずや少量の副菜を作るときには、16cmの片手鍋がとても便利です。
卵をゆでたり、ほうれん草を少しだけ茹でたり、ちょっとした煮物を作るのに使いやすく、後片付けも簡単です。
18cmの鍋でももちろん作れますが、量が少ないとお鍋の中で具材が広がってしまい、調理しづらいと感じることもあります。
そのため、「少しだけ作る」用途には16cmが断然扱いやすいです。
逆に、作り置きやお弁当用にまとめておかずを作っておきたい方は18cmを選ぶと一度に調理でき、忙しい朝の時短にもつながります。
用途やライフスタイルによって、16cmと18cmを使い分けるのがベストです。
4. 人気ブランドとおすすめモデル
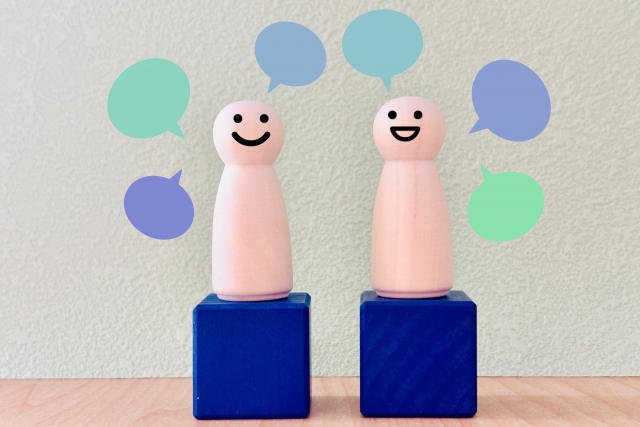
4-1. 定番の日本製:柳宗理・富士ホーロー
日本の台所に長く愛され続けている定番ブランドが「柳宗理(やなぎ そり)」と「富士ホーロー」です。
どちらも素材やデザインにこだわりがあり、初めての片手鍋でも安心して選べる信頼感があります。
・柳宗理の片手鍋は、ステンレス+アルミの三層構造で熱がムラなく伝わり、焦げ付きにくく日常使いにぴったりです。
注ぎ口が両側にあり、蓋をずらして湯切りもできる機能美あふれる設計が魅力です。
・富士ホーローは、ホーロー素材の温かみあるデザインと色展開が魅力です。
コットンシリーズのようにパステルカラーで揃えられるラインもあり、見た目のかわいらしさを重視したい方にも好評です。
4-2. コスパで選ぶなら?(ニトリ・無印など)
「気軽に試せるお手頃価格」が魅力なのが、ニトリや無印良品の片手鍋です。
・ニトリは、販売数が多く価格が手ごろな割に、ふっ素コーティングや注ぎやすい工夫がされたモデルなど、機能性もそれなりにあります。
「無理なく買えて、料理が楽になる」気分を得られるブランドです(複数メディアでコスパ重視として紹介されています)。
・無印良品も、ミニマルでシンプルなデザインが好きな方にぴったり。
ただし具体的な言及は少ないものの、「選びやすさ」として注目されるブランドです。
4-3. おしゃれさ重視のブランド(北欧風・カラー鍋)
見た目のかわいさやおしゃれさを大切にしたい方には、北欧風やカラー展開があるブランドがおすすめです。
たとえば、ホーロー素材でデザインもキュートなものがたくさん見つかります。
・「おしゃれ&かわいい」片手鍋特集にも、ル・クルーゼやティファール、柳宗理、ニトリと並んで紹介されており、カラフルさやデザイン性を重視する方から支持されています。
・また、ホーローなら注ぎ口付きのミルクパンは使いやすさも兼ね備えており、北欧風インテリアにも自然になじみやすいです。
4-4. 実際に売れている片手鍋ランキング(Amazon・楽天)
実際にネット通販で「売れている片手鍋」を見てみるのも参考になります。
・オールアバウトBestOneやマイナビ、おすすめメディアでは、16cm・18cmを中心に、柳宗理やル・クルーゼなどの人気ブランドがランキングに並んでいます。
・楽天の販売ランキングでも、「柳宗理 片手鍋」などが上位に並んでおり、レビューをチェックすると「使いやすく長く使える」という声が多いです。
5. サイズ選びのチェックリスト

5-1. 家族人数と食生活で考える
片手鍋を選ぶとき、まず基準にしたいのは「家族の人数」と「普段の食事スタイル」です。
例えば一人暮らしであれば、16cmの片手鍋があればほとんどの料理に対応できます。
二人暮らしでも「外食が多くて自炊は軽め」という場合は16cmが便利です。
一方で、三人以上の家庭や、日常的にしっかり自炊をする方は18cmを選ぶと安心です。
特に子どもがいるご家庭では、思った以上に「汁物や煮物を多めに作る」ことが増えるので、大きめサイズを選んでおくと後悔しません。
家族の人数だけでなく「どれくらい自炊するか」を意識すると、自然と答えが見えてきます。
5-2. よく作る料理で選ぶ
次に考えたいのは「自分がよく作る料理」です。
味噌汁やスープのように毎日少量ずつ作る料理が多いなら16cmが最適です。
少量をこまめに作れるので、いつも新鮮な状態で食べられます。
逆に、カレーやシチュー、煮物のように「まとめて作って次の日も食べたい」という料理が多いなら18cmが活躍します。
一度にたっぷり作れるので、時間の節約や光熱費の節約にもつながります。
ラーメンやパスタをよく食べる方も要注意。
一人分なら16cmでも大丈夫ですが、二人分以上を一度に作るなら18cmの方がストレスなく調理できます。
つまり「自分の定番メニュー」に合わせてサイズを選ぶことが、いちばん失敗しないコツです。
5-3. キッチンスペース・収納とのバランス
もう一つ見逃せないのが「収納スペース」です。
16cmの片手鍋はコンパクトで軽く、狭いキッチンやワンルームのシンク下にも収まりやすいです。収納力が限られている場合には16cmを選んだ方が使いやすさを実感できます。
18cmはやや大きいので、他の鍋やフライパンと重ねるときに少し場所を取ることもあります。
ただし、その分多用途に対応できるので、「スペースに余裕がある」または「調理の便利さを優先したい」という方には18cmが向いています。
キッチンがコンパクトな方は、16cmを基本にして「どうしても必要になったら18cmを追加する」という二段構えの考え方もおすすめです。
5-4. 「16cmと18cmどっちにすべき?」判断フローチャート
最後に、迷ったときのために簡単なチェックフローチャートをご紹介します。
Q1. 家族は2人以内?
→ YESなら16cmがおすすめ。
→ NOなら次の質問へ。
Q2. まとめて作り置きすることが多い?
→ YESなら18cmがおすすめ。
→ NOなら次の質問へ。
Q3. キッチンがコンパクトで収納スペースが少ない?
→ YESなら16cmで省スペース。
→ NOなら18cmで便利さを優先。
このように、人数・料理のスタイル・キッチンスペースの3つを基準にすれば、自分に合った片手鍋のサイズを簡単に見極められます。
迷ったときはこの流れをチェックしてみてくださいね。
6. まとめ|片手鍋サイズの選び方の結論

7-1. 16cmと18cm、それぞれのメリット再確認
ここまで、16cmと18cmの片手鍋について詳しく見てきました。
改めて整理すると、16cmは「コンパクトで扱いやすい」「二人暮らしや少量調理にちょうど良い」という点が魅力です。
軽いので毎日使う鍋として気軽に取り回せ、収納にも困りません。
一方、18cmは「作れる量に余裕がある」「家族向けの料理や作り置きに便利」という特徴があります。
少し大きめなので多少重さはありますが、その分さまざまな料理に応用でき、安心感のあるサイズです。
どちらが優れているというよりも、「自分の暮らし方に合っているかどうか」が選び方のポイントになります。
6-2. 迷ったらどちらを選ぶべきか
もし「16cmと18cm、どっちにしようか本当に迷っている」という方には、次の基準をおすすめします。
・自炊は軽めで、毎日の味噌汁やちょっとした副菜が中心 → 16cm
・家族が3人以上、またはカレーや煮物をまとめて作ることが多い → 18cm
さらにスペースや予算に余裕があるなら、16cmと18cmの両方を持つのも実はおすすめです。
普段は16cmで少量を作り、作り置きや週末の料理には18cmを使うなど、シーンによって使い分けるととても快適です。

